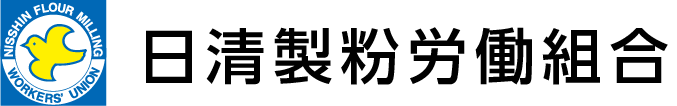IUF-JCC 海外労働学校―スウェーデン・スイスー
- 2025.08.25
第46回IUF-JCC海外労働学校に本部より西村書記次長が参加しましたので、報告します。
<海外労働学校とは>
日清製粉労働組合の上部団体であるフード連合や、最大の産別組織UAゼンセンなどが加入している国際労働機関IUF-JCC(国際食品労連 日本加盟労組連絡評議会)が主催する研修です。
①国際労働運動や国際連帯の意義、②多国籍企業の社会的責任と労働組合の役割、③訪問国の文化や社会 などを学ぶことを目的に実施されています。
ここでは今回の研修の中でもテーマを絞り、スウェーデンの労働組合の特徴とUNHCRの活動について記載します。
<スウェーデンモデルについて>
スウェーデンといえば、高福祉・高負担の国として知られていますが、その背景には、「スウェーデンモデル」と呼ばれる独自の社会経済制度があり、労働組合・使用者団体・国家の三者が互いに補完し合う協調的な関係によって築かれています。スウェーデンの労働組合は、産業ごとに組織されており、強い交渉力を持ち、労働条件や賃金を取り決める中心的な存在です。それに対して使用者は、企業側の立場から、労働組合との団体交渉に参加し、持続可能な経済活動を守る役割を担っています。そして国家は、この両者の自律的交渉を尊重しながら、必要に応じて法制度を整備し、雇用保険や教育制度などの社会的基盤を提供しています。この「三者の対等な協力関係」により、政府の過度な介入に頼ることなく、現場に近いところで柔軟な合意形成が可能となっていて、労使が定めた協約がそのまま実質的な労働ルールとなります。あくまで国家はそれを補完・支援するいわば仲介役のような立場にとどまっています。つまり。スウェーデンでは、労働組合が労働市場の制度設計者の一翼を担い、「生活インフラの一部」としての役割を果たしているということが大きな特徴です。
今回、Livs(食品労働組合)という1922 年に設立されたスウェーデンの食品労働者を代表する産業別労働組合を訪問し、話を聞いてきました。日本の労働組合と同じように賃金・労働時間・安全衛生の団体交渉や福利改正の改善なども行っていますが、その他にも差別反対、移民労働者の支援(多言語対応)、食品産業特有の安全基準の確立、デジタル監視(AI/IoT)の労働者影響に関する提言、気候変動への対応(環境配慮と雇用の両立)など食品業界全体に波及する取り組みも行っていて、労働組合の存在感・影響力の大きさを改めて時間しました。
私たち日本の労働組合は、企業単位での交渉が中心で、産業全体を代表するような団体交渉は一般的ではありません。しかし、単に自分たちの会社の労働条件を守るだけでなく、一人一人が社会をより良くしていこうという意識を持つことがとても大切であり、フード連合などの上部団体と連携し、産業ごとの課題解決に取り組んでいくことが求められていると感じます。
<UNHCRの活動について>
UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は、戦争や迫害により故郷を追われた人々を保護し、支援するために設立された国連の専門機関で、1950年に国連総会によって設立され、当初は第二次世界大戦後に欧州で発生した難民問題に3年間限定で対応する臨時機関として活動を開始しました。しかし、その後も世界各地で紛争や人権侵害が相次ぎ、UNHCRの任務は延長され続け、現在では約2万人近くの職員が約130か国で活動する国際機関となっています。
そもそも難民とはどういった人々の方を指すのか知っていますか?1950年UNHCR事務所規程、1951年難民条約、1967年難民議定書において、「人種、宗数、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で、自国にいると追害を受けるおそれがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々」と定義されています。この定義では、自国における平時と戦時の区別をしておらず、国際的・国内的な武力紛争や戦争から他国に逃れてきている人々も、上記の定義に該当するのであれば難民としています。さらに、紛争や迫害により自国の中で元の住居を離れて避難している人々は国内避難民と言われていて、その数は増加しているのが実態です。
UNHCRは難民の人々のためにいったいどんな活動をしているのか一例を挙げると、到着した難民の登録、食料・水・医療・住居・教育などの提供、コミュニティ活動の支援、メンタルサポート、職業訓練、ごみ処理場の確保、道路の建設など多岐にわっていて、いわば一つの村づくりを行う役所のような役割を果たしているとも言えます。しかし、UNHCRだけでその全てを現場レベルで実行することは困難であるため、多くのNGOと協力関係を結ぶことで支援を進めることができているそうです。
こういった支援活動のほかにも、難民の根本的な解決に向けての活動も行っていて、その解決策は3つあると言われいます。
①自主帰還:難民が自発的かつ安全に母国へ戻る
②第三国定住:母国でも避難先でもない第三国に定住する
③庇護国による社会統合(現地定住):避難先である庇護国に定住し、社会的に定着する
現実的な選択肢としては、「庇護国への定住」が最も多くなっていますが、庇護国の多くが決して豊かではなく、政治的に安定していないこともあり、大勢の難民を受け入れることが大きな負担になっている現状があります。それに対して、「第三国定住」は難民を庇護国から移動させることで人道支援を行うためのスペース(余裕)を作ることにつながるだけでなく、庇護国だけが難民の責任を負うのではなくて、第三国として「私たちも心配している・助けてあげたい」というメッセージを伝える大切な方法にもなります。もちろん、「なぜ第三国が難民を受け入れなければいけないのか」という国もありますが、第三国定住は難民の中でも小さい子供抱えている家庭や、持病を抱えている人など助けを必要としている人々をターゲットとしている中で、人道支援に基づいた思想から、第三国定住を受け入れているという国もあり、その支援の輪は広がっています。一見、難民の受け入れは難しくてお金もかかるというイメージがありますが、長い目で見ると難民が来たことで、経済的にも社会的にもプラスの効果を生み、受け入れ国の社会に貢献している事例も見られていて、難民は受け入れ国にとって「負担となる存在」という考え方ではなく、「貢献してくれる存在」となる可能性も秘めているのです。昨年はUNHCRとして90か国から難民の人を推薦して21か国の国が受け入れていて、その中には日本も入っています。日本はアジアで初めて第三国定住を始めた国で毎年60人程度の受け入れを行っているそうです。
日本で暮らしていると、難民問題はどこか遠い国の出来事のように感じられますが、世界には戦争や迫害によって日常を失い、命からがら逃げている人々が大勢いる。その現実を今回の訪問を通して改めて知ることができました。難民の受け入れを進めていく上での課題として、治安や負担への不安などから、難民がひとくくりに「迷惑な存在」と捉えられてしまっている部分もあるのではないかと思いますが、難民とは決して特別な存在ではなく、私たちと同じように家族を持ち、夢や希望を抱きながら生きている一人の人間であって、背景や境遇は違っても、そこには個々の人生があることを忘れてはならないと強く感じました。「難民」という大きな枠で一括りにするのではなく、一人ひとりに耳を傾け、尊厳ある存在として向き合う姿勢が求められているのだと思う。まずは自分自身が正しい知識を持ち、無関心でいないこと。それが、今の自分にできる最も小さくて、けれど確かな第一歩だと思います。

(写真:ジュネーブのILO(国際労働機関)での集合写真)
以上
- 1